ハンス・クリスチャン・アンデルセン『絵のない絵本』×メンデルスゾーン『無言歌』小説を彩るクラシック#18
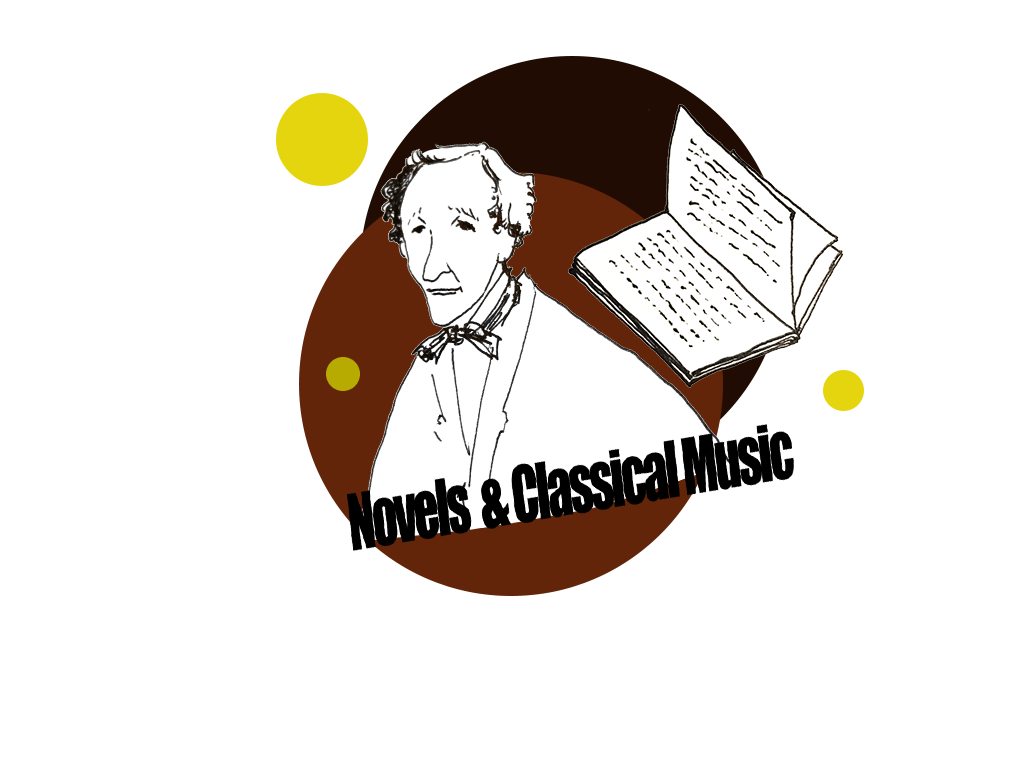
その子は肩の荷物をおろしました。青ざめた美しい顔が、なにかこううかがうように、森のほうへむけられて、目のきらめきは、海原はるか大空のなかを見あげているといったふぜいなのです。両手をくみ合わせていたところからみると、きっと神さまにおいのりしていたのでしょう、その子の胸をつらぬきながれた感情のことは、彼女じしんにもはっきりとは理解できなかったのですが、でも、わたしはよくわかっていました──この瞬間と彼女をとりまくこの自然の思い出は、たとえ数年ののちになっても、かならずやこの子の眼前にありありと、よみがえるばかりではなく、あのえかきがかぎられた絵の具で、紙の上にえがきえたすがたよりもはるかに美しく正確に、思いだされるであろうことも──。
意気揚々と森のスケッチをする画家が描く絵よりも、月は貧しい少女の瞳が捉えた風景──彼女の内面にフォーカスします。ものとして残るものよりも、一瞬が捉えたもののほうが美しい時がある、と読者に伝えてくれる場面です。
アンデルセンは自ら「旅は人生の学校だ」と語る通り、旅から多くのことを学び、出会い、創作の糧にしてきました。
想像すること──自分の目で見て、自分の耳で聞くこと。『絵のない絵本』に絵はありません。だからこそ自由に私たちの想像力を羽ばたかせてくれます。
参考文献
アンデルセン(2010年)『絵のない絵本』
川崎芳隆訳 角川文庫










この記事へのコメントはありません。