スチュアート・ダイベック『冬のショパン』× ショパン『ワルツ』と『夜想曲』 小説を彩るクラシック#4

フレデリック・ショパン『夜想曲』
マーシーは、ワルツだけではなく、前奏曲、練習曲、バラッド、マズルカ、ポロネーズとショパンの代表曲を毎晩弾き続けます。
マイケルとジャ=ジャは、「あれは何だ?」「これは何だ?」と言い合いながら、マーシーの演奏を楽しみにするようになり、マイケルもその演奏を聴いて、ショパンのどの曲かを答えられるようになっていきます。
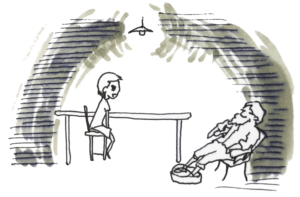
そんなマーシーが、一度だけショパン以外のものを弾くシーンがでてきます。それが「ブギウギ」です。
ジャ=ジャはブギウギを知らないマイケルに「がやる音楽だ」と説明して、マイケルの母親にたしなめられます。マーシーがショパン以外のピアノを弾くのはこの一度だけ。
ある晩からマーシーはピアノを弾くことをやめてしまいます。それによって、ジャ=ジャの元気もなくなっていきます。
マーシーがピアノを再開したのは冬が終わる頃でした。弾くのはもっぱら夜想曲だけ。しかもそれは凄く小さな音で、夜の深い時間に弾かれていました。マイケルはベッドに寝転がりながら、その夜想曲に耳を澄まします。
やがて冬が終わり、マーシーは突然手紙を残してアパートから消えてしまいます。
ミセス・キュービアックは取り乱し、落ち込み、毎朝、バブーシュカをかぶり、喪服を着て過ごし、一気に老け込んでしまいます。それは「旧世界からやって来たほかの女の人たちと見分けがつかなくなっていた」と作中で形容されています。
月日が経ち、マーシーから手紙が届きます。そこには「サウス・サイドのシカゴ大学近辺の黒人街に住んでいたこと、息子が生まれたこと、息子にはテイタム・キュービアックと名付けたこと」が記されていました。

テイタムという名前は、超絶技巧を持つジャズ・ピアニスト、アート・テイタムの名前にあやかってのことです。
この小説はある冬の小さな家族たちが描かれるわけですが、マーシーの弾くピアノを通して、クラシック(旧世界)からジャズ(新世界)へ移行していくシカゴという街を表しているようにも思えます。
マイケルというまだ色のついていない透明な視線を通して描かれることで、旧的なもの、新的なもの、どちらに肩入れすることなく描かれているのがこの小説の魅力の一つでしょう。
そして、この小説を彩るショパンは、手に取って触れることができるのでは? と思うぐらいリアルで、我々の心情に迫ってきます。クラシックファンにも、小説好きな方にも是非読んでいただきたい一冊です。
参考文献
スチュアート・ダイベック(2003年)『シカゴ育ち』“冬のショパン” 柴田元幸訳 白水Uブックス










この記事へのコメントはありません。