ジョージ・ガーシュイン|George Gershwin 1898-1937
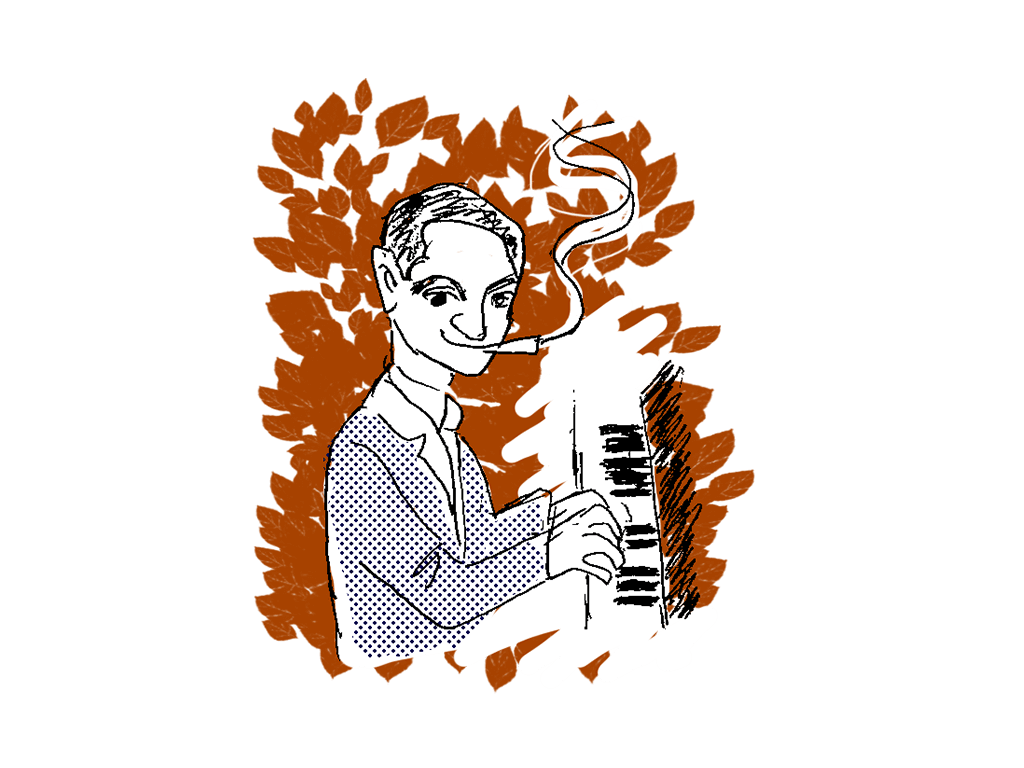
ジョージ・ガーシュイン
George Gershwin
1898年9月26日-1937年7月11日
アメリカ合衆国 ニューヨーク ブルックリン生まれ,ロサンゼルス没
管弦楽曲『ラプソディ・イン・ブルー』、『パリのアメリカ人』やオペラ『ポーギーとベス』で著名なジョージ・ガーシュインは、ジャズとクラシック音楽の融合で成功し、現代につながるアメリカ音楽を作り上げた作曲家として世界的に評価されている。
ジャズ、ポピュラー音楽(以下ポップスと呼ぶ)の作曲家なのか、クラシック音楽(以下クラシックと呼ぶ)の作曲家なのかという疑問について、一般的にはその両方で活躍した作曲家として紹介されることが多いが、二つを明確に区別すること自体が無意味であると思わせてくれる、極めて優れた作曲家であることは誰も異論を挟めないところであろう。
38歳という若さで亡くなったが、オペラやミュージカル、映画音楽、歌曲、ピアノ曲などを含めて、多彩な作品が遺されている。レナード・バーンスタインピアノ&指揮、ニューヨークフィル演奏による『ラプソディ・イン・ブルー』や、小澤征爾指揮、ベルリンフィル演奏による『パリのアメリカ人』など、クラシックの場面における名演は多い。
ガーシュインの生涯
生い立ち
1898年9月26日、ニューヨークのブルックリンで、教育熱心なユダヤ系ロシア人移民の両親のもと、4人兄弟の次男として生まれた。兄のアイラ・ガーシュイン(1896~1983)は言わずと知れたポップス、クラシックの作詞家で、様々な作品を遺しているが、弟ジョージと組んだ作品も多く、ミュージカル歌曲『アイ・ガット・リズム』などは現在でも光を放つ名作である。
両親が兄アイラに習わせようと譲り受けた中古ピアノに、当のアイラ自身は興味を持たず(兄は文学に夢中であった)、むしろ弟のジョージの方が惹きつけられ、音楽の道を歩むことになる。それには、既に近所の友人宅のピアノに触れていたこと、町に流れる流行りのラグタイムに触れていたことも影響したであろうが、ドヴォルザーク(1841~1904)の『ユーモレスク』や、ルービンシュタイン(1887~1982)の『へ調のメロディ』といったクラシックから感動を受けた経験も大きかったのではないかと思われる。
商業学校時代13歳の頃から本格的にピアノ、音楽理論を習い、クラシックピアニストを目指すが、ピアノの師の死去によりその道を断念する。15歳の時に商業学校を辞め、大手楽譜出版社リミック社でピアノ楽譜の商業宣伝ピアニスト、ソングプラガーとしてプロの道を歩み始める。※1
当時のニューヨークでは、音楽出版社が軒を並べたティン・パン・アレーと呼ばれる地域からマディソン・スクエア・ガーデン付近にかけて、ラグタイム※2 の生演奏を聴かせるカフェがたくさんあったそうで、出版社一番の売れ筋であるラグタイムの演奏テクニックを磨くため、ジョージは黒人ピアニストの生演奏を聴かせる店に通いながらラグタイムに造詣を深めることになる。
仕事場では楽譜により職業的な音楽知識を学び、またカフェでは体感的にラグタイムの演奏を浴び、全身で生の音楽教育を受けていったのであった。
※1 当時の音楽界はまだレコードが一般に普及していなかったため楽譜を売るのが主流であった
※2 ジャズの源流の一つで主にピアノ演奏による。ジャズと呼ばれる以前のジャズはラグタイムミュージックと呼ばれていた
作曲家としての歩み
商業学校時代から流行歌の作曲を試みていたガーシュインは、リミック社の看板ピアニストに上り詰め、18歳の頃から本格的に作曲活動を開始する。最初は他の作曲家のミュージカルやレヴュー作品などの一部を穴埋めするような活動が多かったが、20歳を前にしてリミック社を辞め、伴奏ピアニストを務めたり、他の出版社に在籍し自らの作品を提供したりして生計を立てるようになる。
そして1919年、21歳を目前に作曲したミュージカル『ラ・ラ・ルシール』がブロードウェイで100日を越えるロングランとなる。また、21歳の誕生日を挟んで発表されたレヴュー用の1曲『スワニー』を、ブロードウェイの人気歌手であったアル・ジョルソンが取り上げ、これがガーシュインにとってもジョルソンにとっても代表曲となる程の大ヒット曲となる。楽譜売り上げは100万部を超え、1920年に録音されたレコードは225万枚の爆発的売り上げを記録した。
ジャズ王との出会い
ガーシュインが流行作曲家としての歩みを始めた頃、ニューヨークのポップス界ではラグタイムに代わって南部ニューオリンズ生まれのデキシーランド・ジャズ※3 が流行り始めた。
デキシーランド・ジャズの魅力に目を付け、自らのオーケストラによる演奏でその人気を急激に高めたのは、作曲家、バイオリニストのポール・ホワイトマンであった。自他ともに[ジャズ王]と認める存在となった彼は、ジャズを芸術としてより高いレベルに押し上げたいと考えた。その一環として、『現代音楽の試み』という、現代アメリカ音楽とは何かを審査員団が審査するという趣旨のコンサートを企画するが、彼は、ガーシュイン本人に知らせないまま、ガーシュインがプログラムとして[ジャズ・コンチェルト]を制作中であることをニューヨーク・トリビューン紙の紙面に発表してしまう。
企画が盗まれることを危惧してギリギリまで発表を伏せていたとも、ガーシュインが断れなくするための作戦だとも言われるが、ガーシュイン本人の驚きと困惑は如何ばかりであっただろう。新聞発表は1月3日、公演は2月12日。時間はない。しかし、依頼主ホワイトマンの情熱、そしてクラシック界でも作曲家として成功したいという自らの意志が、このエポックメイキングな瞬間を生むことになる。ジョージ・ガーシュインの一番の代表作『ラプソディ・イン・ブルー』の誕生である。
※3 ラグタイムやブルースなどを融合して成立。ピアノやドラムのリズムセクションと管楽器セクションによる合奏が原型
クラシックとして認められたシンフォニック・ジャズ
クラシック音楽、いや全ての音楽における歴史の中で、最も重要な作品の一つである『ラプソディ・イン・ブルー』は、1924年、ジョージ・ガーシュイン25歳の時の作品である。納品期日までに1ヶ月しかない中、頭の中に鳴り響く音楽に対してオーケストレーションの知識に充分に精通していなかった彼は、どのようにしてこの難局を乗り越えたか。
それはまさに神技であった。仕事で向かうボストン行きの汽車の中、最初から最後まで全ての曲想が思い浮かんだガーシュインは、自らの得意なところで2台のピアノによる曲として作曲、先述のホワイトマン・オーケストラのピアニスト兼アレンジャーであったファーディ・グローフェが直ちにオーケストラ曲に編曲していったという。その間わずか2週間。
それに加えて、クラリネット奏者のアイディアによる冒頭の特徴的なグリッサンド演奏、兄アイラのアイディアによる『ラプソディ・イン・ブルー』というキャッチーなタイトル(当初は『アメリカン・ラプソディ』というタイトルが用意されていた)も相乗効果を生み、ガーシュイン本人のピアノ、ホワイトマンの指揮でこの新しい作品は大成功を収めることになる。
この演奏会には、当時アメリカに移住していたラフマニノフをはじめとして、ストラヴィンスキー、バイオリニストのクライスラーなど、多くのクラシック界の重鎮が立ち会っており、そんな中スタンディングオベーションに包まれたガーシュインの心はどれほど興奮したであろう。このピアノ協奏曲風のジャズ・コンチェルトは[シンフォニック・ジャズ]として高く評価され、ここにクラシック作曲家、ジョージ・ガーシュインが世界に向けて華々しく船出することになるのである。
尽きることのない作曲意欲
それまでも作曲家としては売れっ子のガーシュインであったが、『ラプソディ・イン・ブルー』の成功によって、クラシックの作曲意欲がますます増していく。少なからずコンプレックスを感じていたオーケストレーション技術について、多忙な仕事の合間に独学で学んでいく中、2つの興味深いエピソードがある。オーケストレーションについて全くの無学ではなかったこともあり、その後の独学により既にピアノ協奏曲を書き上げていた彼は、さらにクラシックのオーケストレーションについて学ぼうと、2人の大作曲家に教えを請う。
1人は20世紀を代表する作曲家で色彩派オーケストレーションの巨匠、ストラヴィンスキーである。ストラヴィンスキーはこのオファーを丁重に断っているのだが、その時「こちらこそどうやったらあなたのように収入を上げられるか教えを請いたい」と言ったという話がまことしやかに伝わっている。これは事実ではないようだが、ストラヴィンスキー自身は後々「そのようなことがあったら楽しかっただろうに」と言ったそうで、心温かくなるエピソードである。
もう1人は、やはり20世紀を代表する作曲家で、オーケストレーションの天才と称されるラヴェルである。こちらも印象的な言葉が伝わっていて、そのオファーを断る際に「あなたは既に一流のガーシュインなのだから、二流のラヴェルにならなくてもいいではありませんか」と言ったという。ラヴェル自身、ジャズに大きな感銘を受けていたこともあり、若き天才であるガーシュインを作曲家として同等に認めていたと思われる。
そうしてガーシュインは独学により、クラシックとしての管弦楽曲『パリのアメリカ人』(1928年)を生み、オペラ『ポーギーとベス』(1935年)を生み、並行してポップスとしてのミュージカル作品、映画音楽を生み出し、尽きることのない意欲を持って、精力的に創作活動を行ったのであった。
夭逝の天才の残したもの
エンターテインメントの国アメリカ合衆国において、ジョージ・ガーシュインは全ての音楽の場面で超多忙を極め、その才能は最期まで創作活動の手を休めることがなかった。そして仕事が彼の手を離してくれないまま、1937年、39歳を目の前にした7月、脳腫瘍のため短すぎるその人生を閉じてしまった。
音楽学校といったアカデミックな場所で系統立ったクラシックの専門教育を受けずして、クラシックの一局面を切り開いたガーシュインは、やはり天才だったと言える。しかし、その天才の意味は、音楽の神に愛されただけではなく、音楽に尽きることのない情熱を持ち、音楽からひと時も離れず、音楽にその身を全て捧げる才能のことではなかったか。
折しも後期ロマン派を引きずりながら多様な新しいものを含む近代音楽へとクラシックの流れが移っていた時代、ナチスドイツから逃れて1934年にアメリカに移住してきたシェーンベルクと親交を持ち、彼の創始した十二音技法などの新しい技法に興味を持っていたガーシュインは、もしその後もう少しばかり人生を永らえていたとしたら、さらなる新境地に達したかもしれないと思うのは、欲張りな幻想かもしれない。
しかし、その後のアメリカ音楽には、クラシックとポップスの両方の要素を豊かに含みこむ芸術音楽の流れが綿々と確かに続いている。アーロン・コープランド然り、レナード・バーンスタイン然り、ジョン・ウィリアムズ然り。その流れを切り開いたジョージ・ガーシュインが、[アメリカ・クラシック音楽の父]として、この先永遠に語り継がれる作曲家、音楽家であることは疑いようのない真実である。









この記事へのコメントはありません。