ヘルマン・ヘッセ『荒野のおおかみ』×モーツァルト 小説を彩るクラシック#17

ヘルマン・ヘッセ『荒野のおおかみ』
1927年、第一次世界大戦の終結後、世界は文明が過剰に発展していき、物質的なものが尊ばれる時代になっていました。
ヘッセは、世界大戦後から作風を一変させ『デーミアン』(小説を彩るクラシック#14)、『シッダールタ』を発表。そして、文明の批判と、自己の内面を描いた、『荒野のおおかみ』を発表します。
『荒野のおおかみ』
主人公の名前はハリー・ハラー。
ヘルマン・ヘッセと同じイニシャルを持つ、作者の分身ともいえる50歳手前の男です。ハリーは、芸術を信奉する孤独な男で、ゲーテとモーツァルトを愛し、他人に心を開くことなく、自らを“荒野のおおかみ”と称し、自己と世界との間の分裂に苦悩するアウトサイダーとして描かれます。
ストーリー
物語の序文では、大家の甥が“荒野のおおかみ”の特異性(異様で、野性的で、内気)について語り、次の章では、「ハリー・ハラーの手記」が置かれます。
手記でハリーは、孤独と狂気について語り、酒場で杯を重ねながら、永遠について夢想します。
私は永遠なものを、モーツァルトを、星を思い出させられた。私はまた一時間呼吸することが、生きることが、存在することができた。
次に「荒野のおおかみについての論文 狂人だけのために」では、客観的にハリー・ハラーについての分析的な叙述。
ハリーは、高い教養のある人間であるにもかかわらず、二つ以上数えることのできない野蛮人のように振舞っている。
論文の中ではこのように書かれています。
彼はあくまで、孤立した人間であり、変わり者の病気の隠者であり、非凡な天才であり、ブルジョアを軽蔑する人間である。ただ、一方ではまったく市民的な人間である、と。
「市民的なもの」と「オオカミ的なもの」との間の揺れが、この小説を貫くテーマとなります。
![]()
続く「ハリー・ハラーの手記 続き」の章では、旧知の大学教授にディナーに誘われた晩が描かれます。
ハリーは新聞に平和主義(※戦争や暴力に反対し、恒久的な平和を志向する思想的な立場)についての文章を書きましたが、作者を知らない教授は、祖国の裏切者が書いたくだらない文章だ、とこき下ろします。
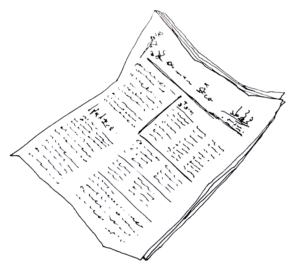
やはり来るべきではなかったと感じたハリーは、教授の家を後にするとき、壁に掛けられたゲーテの肖像を見て、悪態をつきます。
「ゲーテは実際にはこんな顔をしていなかったはずなんですがね」
俗っぽく描かれたゲーテの肖像にも、それを喜んで飾っている教授夫婦に対しても我慢ができませんでした。
絶望の思いで外を歩き、もう救いは「死」だけだ、と感じます。「死」に取り憑かれたまま酒場に辿りついたハリーは、生命力にあふれた女性と出会いました。
ハリーの幼年時代の友だち、ヘルマンの印象をもつ女性は、ヘルミーネ(ヘルマンの女性名、もう一つの作者の分身と考えられる)と名乗りました。
「死」の予感を感じ取ったヘルミーネは、ダンスと享楽の世界にハリーを連れていきます。
マリアという魅惑的な女性と、麻薬を扱う美青年のジャズ・ミュージシャンパブロを紹介し、物語はクライマックスへ進みます。











この記事へのコメントはありません。