村上春樹『風の歌を聴け』×ベートーヴェン『ピアノ協奏曲 第3番』 小説を彩るクラシック#1
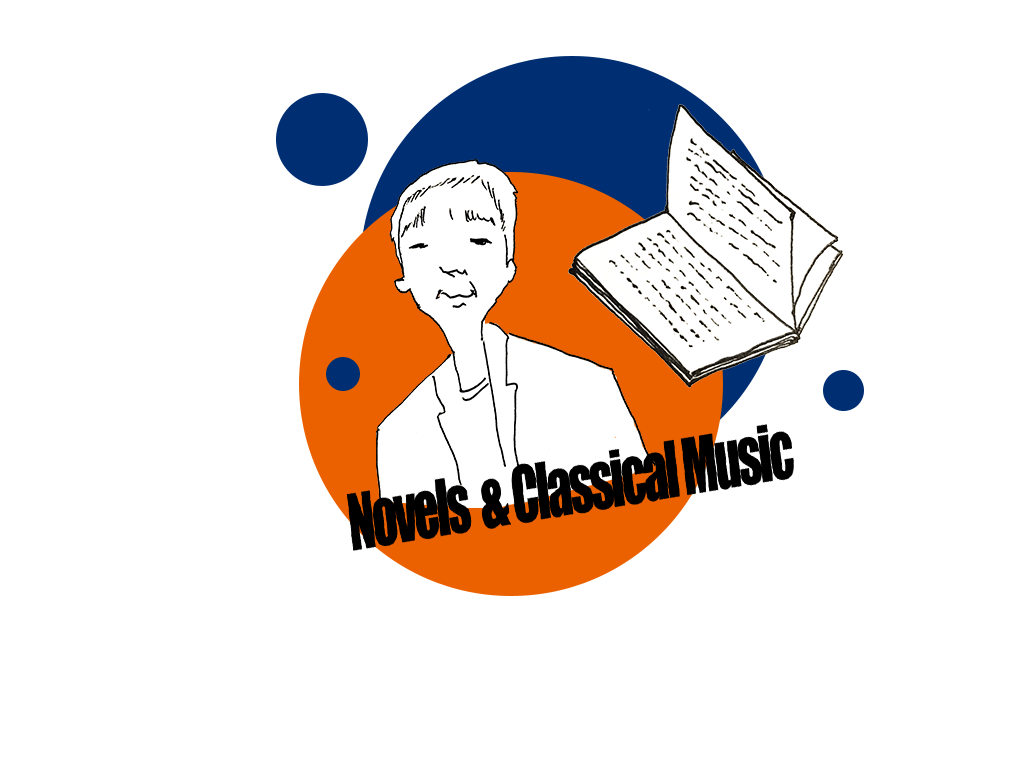
デビュー作にして鼠三部作第一弾!村上春樹『風の歌を聴け』
少年時代にはラジオから流れるビートルズや、ビーチ・ボーイズに胸を躍らせ、学生時代にはジャズ・バーを経営し、日本を代表する指揮者小澤征爾さんとの対談集まで出すという、世界的作家でありながら、無類の音楽好きでレコードコレクターとしても有名な村上春樹。
2021年6月には『古くて素敵なクラシック・レコードたち』という”クラシック”をテーマにした新刊が登場し、クラシックファンの間でも大きな話題になっています。
人生の大半を音楽と共に歩んできた村上春樹にとって、”音楽”、”クラシック”とは、どのような存在なのでしょう。
今回は、デビュー作『風の歌を聴け』の中に出てくる断片から、作家はどのように音楽を登場させ、物語世界を構築しているのかを探ってみたいと思います。
この投稿をInstagramで見る
『風の歌を聴け』
1979年群像新人文学賞受賞作の『風の歌を聴け』で、村上春樹は小説家としてデビューします。
当時の作風は現在のスタイルとは違って、鮮やかで軽やか。バドワイザーとスニーカーが似合うような、”文学”というよりはカルチャー的な雰囲気を持っていました。それは、今までの(所謂)日本文学にはなかった特徴と言えるかもしれません。
あらすじ 映画にもなったある夏の思い出は、特別じゃないのに鮮やかに
舞台は1970年の夏。大学生で主人公の「僕」は海辺にある地元に帰省します。「僕」は友人の「鼠」とバーでビールを飲んで、フライドポテトをかじり、プールに行ったり、ドライブをしたりして退屈な夏を過ごすというもので、特別な”何か”が起きるわけではないんですが、軽やかさの中にちょっとした切なさのようなものを感じる魅力的な小説となっています。
ベートーベンのピアノ・コンチェルトの3番
この小説で登場するクラシック音楽は、主人公の「僕」が友人の「鼠」に渡す誕生日プレゼントとして登場します。
港の近くを散歩中の「僕」は、目についた小さなレコード店のドアを開けます。そこには以前、酔いつぶれていたところを介抱したことのある女の子が働いている店でした。バツの悪い彼女は「何故ここで働いてるってわかったの?」とつっけんどんな態度をとりますが、「僕」は、あくまで偶然だ、と彼女に言います。そして彼女から3枚のレコードを購入します。
その3枚は「『カリフォルニア・ガールズ』の入ったビーチ・ボーイズのLP」、「『ギャル・イン・キャリコ』の入ったマイルス・デイビス」、そして『ベートーベンのピアノ・コンチェルトの3番』。
彼女は「僕」に「グレン・グールドとバックハウス、どちらがいいの?」と訊ね、「グレン・グールド」と即答しているのが印象的です。
「僕」は買ったレコードを行きつけのバーで、友人の「鼠」に手渡し、「鼠」は、「ベートーベン、ピアノ協奏曲3番、グレン・グールド、レナード・バーンスタイン。ム……聴いたことないね。あんたは?」と言い、「僕」は「ないよ」と答えます。
このあたりのやりとりがとても魅力的ですね。
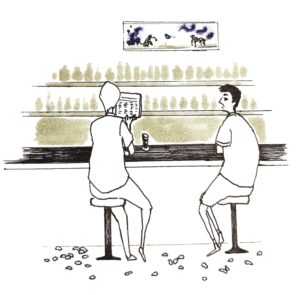
レコードショップで買った3枚も、ロック、ジャズ、クラシックとジャンルがバラバラで、それが、クラシック音楽だけが特権的なものではないということを伝えているようにも思えて、しかも正統的なバックハウス(ベートーヴェン直系の弟子)ではなく、どちらかというと異端児的なグレン・グールドを選んでいるあたりも作者のセンスを伺えます。
作者の好みということもありそうですが、港町で真新しいTシャツを着た若者がふらっとレコード屋を覗き、クラシックのレコードを手に取り、友だちにプレゼントする。物語に直接絡んでくるシーンではありませんが、文学というちょっと“お堅い”世界に新しい風を吹き込んだような、そんな効果を生んでいるように感じます。
『風の歌を聴け』に出てくる音楽が、ロックやポップスだけで、バーで渡すプレゼントがジャズだったら、”キマリ”過ぎていたかもしれません。すべての音楽が日常の延長線上にあり、気取りなどがなく、自然に描かれているのがこの小説の瑞々しい、処女作ならではの美しさなのではないでしょうか。
風のように軽やかに、カジュアルに、クラシックを身近に楽しみましょう。
参考文献
村上春樹(1979年)『風の歌を聴け』講談社文庫
小説を彩るクラシック
ベートーヴェンの記事を読む
グレン・グールドの記事を読む










この記事へのコメントはありません。